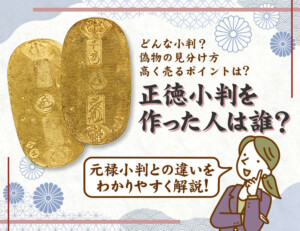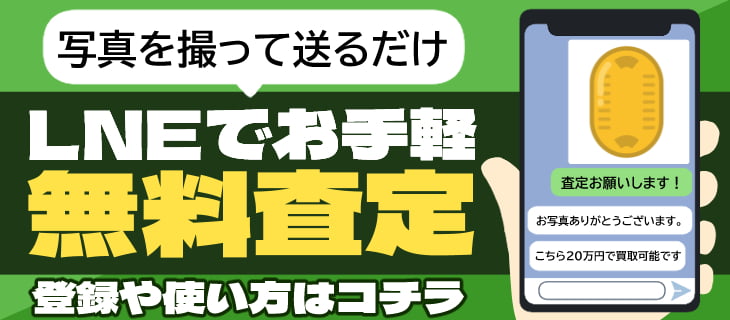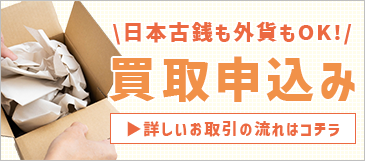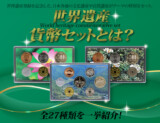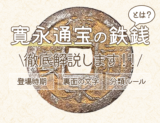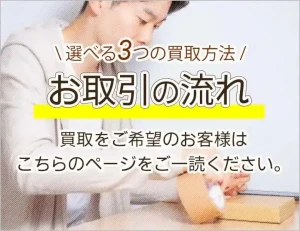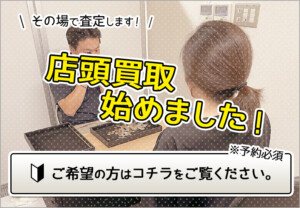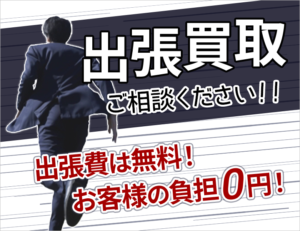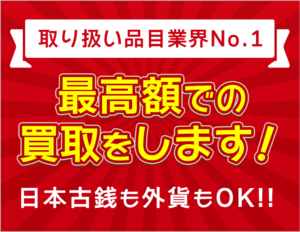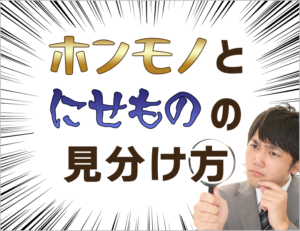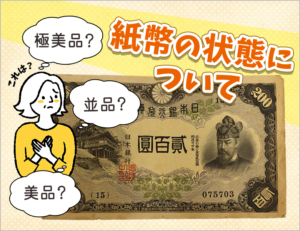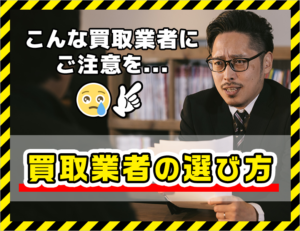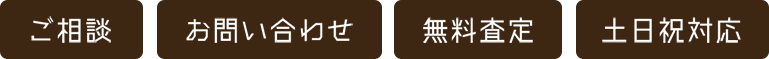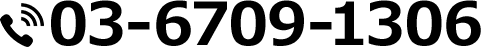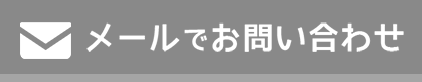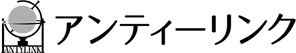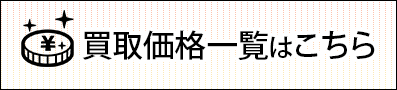享保小判金を作ったのは誰?
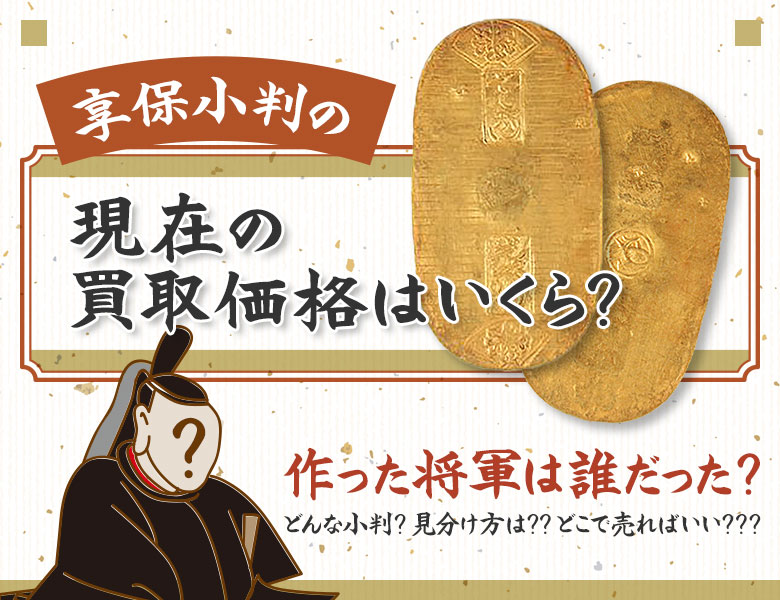
目次
第八代将軍・徳川吉宗が主導して鋳造を担ったのは「金座」
享保小判金は、享保10年(1725年)10月に江戸幕府の命令により、金座で鋳造が開始されました。
発行を主導したのは第八代将軍・徳川吉宗で、これは享保の改革の一環として実施されたものです。
徳川吉宗という人物
徳川吉宗(1684年~1751年)といえば、時代劇の暴れん坊将軍でも有名です。
江戸幕府第8代将軍で、紀州藩主から将軍に就任しました。
享保の改革を主導し、財政再建や社会制度の見直しに尽力したことで知られ、「米将軍」とも呼ばれます。
吉宗は倹約令の実施や年貢制度の改正、公事方御定書の制定などを通じて幕政の安定を図りました。
また、目安箱の設置により庶民の意見を政治に取り入れる仕組みを導入し、医療・教育の振興にも貢献しました。
その政治姿勢は質実剛健で、武士の規律強化にも取り組みました。
享保の改革は長期的には限界もありましたが、江戸幕府中期の統治体制を支える大きな礎となりました。
基本情報:享保小判金
| 項目 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 鋳造開始年 | 正徳4年(1714年)8月 | 幕府の命令による |
| 鋳造場所 | 金座(幕府直属の貨幣鋳造所) | 実務は後藤家らが担当 |
| 主導者 | 徳川吉宗(第八代将軍) | 享保の改革の一環 |
| 品位 | 金含有率 金861/銀139 | 慶長小判金と同等 |
| 量目 | 17.78g | 慶長小判金と同様 |
| 鑑定印 | 裏面に「花押印」(後藤光次) | 年代印はなし |
なぜ享保小判金が必要とされたのか?
享保小判金は、品位を回復させて貨幣の信頼を取り戻す目的で発行されました。
これまでに江戸幕府は、財政難に直面するたびに貨幣の品位(=金や銀の純度)を下げて改鋳を繰り返してきました。
その結果、市場の混乱・物価の高騰・貨幣への信頼低下が深刻になっていました。
改鋳による品位低下の推移
| 小判金名 | 発行年 | 金含有率 | 金含有量 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 慶長小判金 | 1601年 | 85.7% | 15.19g | 基準貨幣とされる |
| 元禄小判金 | 1695年 | 56.4% | 10.04g | 慶長金に比べ29.3%も低下 |
| 宝永小判金 | 1710年 | 83.4% | 7.79g | 品位は回復するも金含有量が低下 |
| 正徳小判金 | 1714年 | 85.7% | 15.19g | 慶長金と同程度に回復 |
| 享保小判金 | 1714年 | 86.1% | 15.31g | 慶長金と同程度 |
正徳小判金でも品位、金の量は回復していた
正徳小判金で金の品位、金の含有量ともに回復しましたが、あくまで宝永小判金発行による混乱収拾を目的とした「一時的な臨時措置」でした。
貨幣制度の抜本的改革ではなく、直前に発行された低品位の宝永小判金による経済混乱の緊急対応として、限定的に鋳造されたものです。
そのため、制度として長期運用されることなく、約1年間の短期間で鋳造が終了しました。
将軍・徳川家宣、政務担当・新井白石の政策により発行されたが、白石の失脚(正徳5年)とともに政策も終息しました。
享保の改革を主導する徳川吉宗の政権下では、白石の一連の政策は引き継がれませんでした。
享保小判金の製造
江戸時代、幕府は貨幣の品質と流通を統制するため、金座を中心に小判金の鋳造を行いました。
享保小判金も伝統的な「手前吹き」方式で製造され、後藤家が検定と極印を担いました。
1. 鋳造を担当した「金座」とその役割
- 金座は、幕府直属の貨幣鋳造所で、小判金や一分金などを製造
- 幕府の命を受けて享保小判金を製造
- 実際の検定・極印押しなどは、金座に属する後藤家が担当
2. 使用された鋳造方式「手前吹き」
- 小判師が自宅などで金を溶かして鋳造(特許制)
- 鋳造後、金座に持ち込んで後藤家が鑑定・極印を押印
- 慶長金から続く伝統的な方式で、享保小判金にも継続適用された
結果として享保小判金は貨幣制度の信頼回復に成功
享保小判金は、1714年からおよそ23年以上にわたって鋳造され続け、その総鋳造量は828万両でした。
享保小判金の影響まとめ
| 影響内容 | 説明 |
|---|---|
| 信頼回復 | 高品位な貨幣として市場に受け入れられた |
| 物価安定 | 改鋳による混乱が一時的に収束し、経済安定へ寄与 |
| 政策成功の象徴 | 徳川吉宗の享保の改革を代表する成功例となった |
| 後の貨幣改鋳へ | しかし1736年には再び品位が下がる「元文改鋳」が行われることとなる |
享保の改革の背景には、将軍・徳川吉宗の強い政治的意志と、貨幣制度の立て直しという経済的課題への対応があったのです。
まとめ:享保小判金は誰が作ったか?
- 鋳造命令者
- 江戸幕府(徳川吉宗)
- 実務担当
- 金座(後藤家を含む)
- 鋳造方法
- 手前吹き → 金座で検定・極印
享保小判金は、将軍・制度・製造現場が一体となって生まれた貨幣であり、その役割は一時的とはいえ、江戸の貨幣経済を支える柱となったのです。
TEL:☎03-6709-1306(営業時間 11:00~18:00)
〒171-0022 東京都豊島区南池袋3丁目18−35 OKビル 501