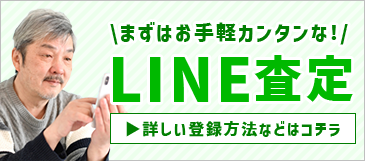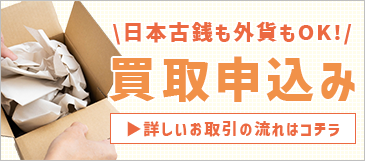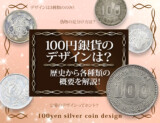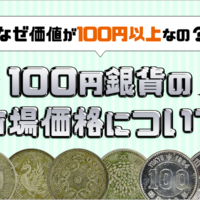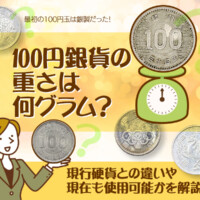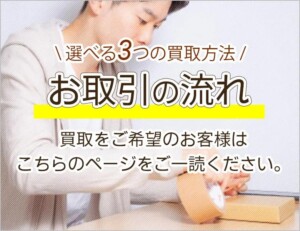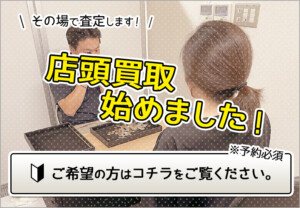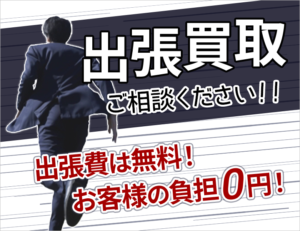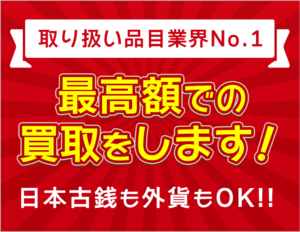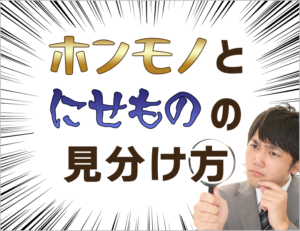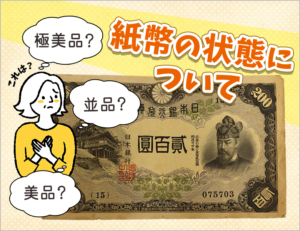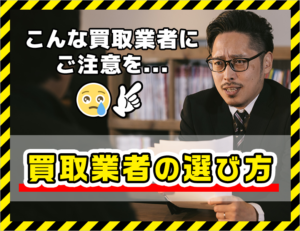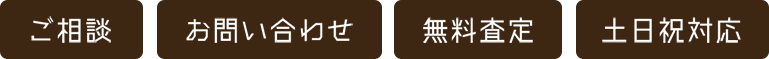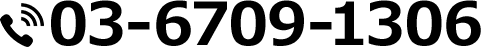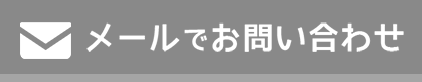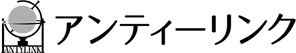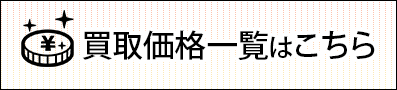100円銀貨の見分け方!それぞれ何が違うの?

この記事では、3種類の100円銀貨の特徴や違いによる見分け方をご紹介します。
100円銀貨は昔使われていた100円玉ですが、全部で3種類あることをご存じですか?
それぞれどのように違うのか、気になりますよね!
2022年、日本唯一の古銭鑑定機関「貨幣商協同組合」に加盟
現在は古銭鑑定士として、テレビ等メディア出演多数
▶︎詳しいプロフィールはコチラ。
目次
3種類の100円銀貨の概要
100円銀貨には「稲穂」「鳳凰」「オリンピック(五輪)」の3つの種類があります。

まずは、そのすべてに共通するサイズ・重さや銀含有量について確認していきます。
- 直径:22.6mm
- 品位:銀60% 銅30% 亜鉛10%
- 重さ:4.8g

100円銀貨は3種類ありますが、違うのはデザインだけです!
100円銀貨の含まれる銀の量
100円銀貨にはおよそ2.88gの銀が含まれています。100円銀貨は大量に製造されているため、希少性からくるプレミア価値が付かないコインです。
ただ、近年銀価格は史上2番目に高い水準にまで上がっていくといわれるほど銀価格は高騰しているため、100円銀貨の価値も銀相場に伴って高騰しています。
詳細記事:100円銀貨の銀の含有量は?
見た目で見分ける方法
100円銀貨とはいわゆる旧100円玉となります。3種類のデザインがありますので、それぞれ確認していきましょう。
鳳凰(ほうおう)が描かれている

表面に羽を広げた鳳凰の図柄および「日本国」と「百円」の文字、裏面には旭日を囲む4輪の桜の花の図柄と「100YEN」の文字、製造年が配されていて、硬貨では当時の最高額面でした。
詳細記事:鳳凰100円銀貨の価値
稲穂(いなほ)が描かれている

なお、この際に五十円硬貨もデザインが変更となり、デザイン案は共に一般公募されました。製造期間は1959年(昭和34年)~1966年(昭和41年)ですが、昭和37年銘のみ製造されていません。
詳細記事:稲穂100円銀貨の価値
五輪マークと聖火が描かれている

1964年(昭和39年)に東京オリンピックが開催され、合わせて100円銀貨のデザインを一部変更した記念貨幣が同年9月21日に発行されました。
この記念貨幣のデザインは、表面に五輪マークと聖火とが、裏面については「100」の字体が少々太く、通常貨幣にはある数字の左右の横線が除かれており、「TOKYO 1964」の文字が追加されています。
年号表記は、「昭和三十八年」のように通常貨幣では漢字で統一されている文字が「昭和39年」の様に漢字とアラビア数字が混在したものとなりました。
2025年(令和7年)時点での銀相場は、1gあたり160〜170円前後で推移しています。
仮に165円とした場合、100円銀貨に含まれる銀としての価格は 165 × 4.8 × 0.6 = 475.2円となり、大幅に額面金額を超えています。
東京オリンピック記念100円銀貨幣が日本初の記念貨幣
日本初の記念貨幣は、この1964年(昭和39年)に発行された東京オリンピック記念100円銀貨幣です。


それ以降も額面金額が100円の記念硬貨が数度発行されており、1982年(昭和57年)の500円硬貨の登場以降は、金や銀などの貴金属を用いたものを除いて、額面金額が500円として発行される記念硬貨が多くなっています。
しかしながら、新幹線鉄道開業50周年記念貨幣や、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念貨幣のように、額面金額が100円で発行される事例も散見されています。
100円銀貨の取引き実績
アンティーリンクでは、これまでたくさんの100円銀貨をお取引きさせていただきました。以下に買取実績の一部をご紹介させていただきます。
| 買取価格 | 買取日 | |
|---|---|---|
| 100円銀貨(76枚) |
13,604円 |
2023年05月31日 |
| 100円銀貨(72枚) |
12,960円 |
2023年08月13日 |
| 100円銀貨(8枚) |
1,376円 |
2023年10月08日 |
| 100円銀貨(23枚) |
4,531円 |
2023年11月16日 |
| 100円銀貨(375枚) |
69,000円 |
2023年12月13日 |
| 100円銀貨(1枚) |
191円 |
2024年02月22日 |
| 100円銀貨(6枚) |
1,446円 |
2024年04月14日 |
| 100円銀貨(121枚) |
33,517円 |
2024年12月28日 |
| 100円銀貨(183枚) |
50,691円 |
2025年01月05日 |
| 100円銀貨(156枚) |
43,212円 |
2025年01月06日 |
アンティーリンクでは、銀相場に連動した買取価格を設定しておりますので、100円銀貨1枚あたりの単価は日々変動しております。
2023年5月は買取金額:179円(1枚あたり)でしたが、2025年1月には1枚あたり277円にまで上がっています。2025年1月20日現在では、やや銀相場が下降し、1枚あたり263円の買取価格となっています。
大きな銀価格上昇の理由は、世界情勢の不安定さ(ロシアや中東での戦争)、太陽光発電市場の拡大に伴う実需の増加(太陽光パネルに銀が使用されるそうです)などと考えられています。
弊社では100円銀貨を高額で買い取ります!
「100円銀貨を売りたい!」「旧100円玉をできるだけ高額で売りたい!」 そんな方はぜひ、アンティーリンクにお売りください。
日々、銀相場によって買取価格の変動がありますので「100円銀貨の買取価格」をチェックしてみてください!
100円銀貨の価値については、以下の記事で解説しています。
合わせて読みたい

TEL:☎03-6709-1306(営業時間 11:00~18:00)
〒171-0022 東京都豊島区南池袋3丁目18−35 OKビル 501
- 投稿タグ
- 100円銀貨の価値